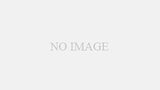御朱印やおみくじ、神様にお願いごとをするために神社に参拝したりしますが、そこで働いている神主さんや巫女さんは普段何をしているかご存知ですか?
「そこで神主って普段何をやっているの?」「これから神主を目指したい!」という方に役立つ情報を、今も神社で奉職している筆者が語ります。
今回の記事を読んで神主を目指している貴方が「ヤバ。無理。」と思っても大丈夫ですし、日本の伝統と歴史を守りたいと思って神社界に挑んでもいいです。
神職の仕事 基本的3種類の仕事
神社にお参りすると、時代劇の衣装のような格好している神主さんやお守りや御朱印等の対応している巫女さんを見て、憧れを持っている人もいるかもしれません。
しかし、実態はこんなもんです。
神職の仕事 例大祭
神職にとって気合いと緊張感を持って取り組む祭祀です。
祈年祭、新嘗祭(にいなめさい)のほか、神社のご鎮座に関わる祭祀が執り行われます。
神職にとって一番重要で大切な仕事になります。まだ慣れていない新人の時期だと、数多くの参列者がいる中で厳かな雰囲気は、緊張で手足が震えたり次の動作が飛んだりしちゃいます。

また筆者がいる神社では、春季例大祭と秋季例大祭の時期に合わせて縁日が並んで、氏子崇敬者や地域の人々も来るので、大いに盛り上がる期間となっています。
しかし、準備が超大変なんです。
実行員会はちゃんと別に存在していますが、彼らのために”準備の準備”があります。
お祭り会場の整備、警察に必要書類を提出したりと、地味で様々な力作業を行っています。(あくまでも筆者が奉職している神社の事例)
それに加えて通常の業務もあるので、超短期の超絶ブラック状態になります。忙しい過ぎてどうやって乗り切ったのか分からないくらい時々記憶が飛んでたりしている一方、学園祭の準備をしている時の妙に興奮した状態にもなります。楽しいですよ。
別の神社に奉職している神主さんを例に出すと、朝の2時半に起床して3時半に出社。4時からお祭りの支度を始めて6時にお祭りを行う。と各神社によって準備の大変さが異なります。
やっと片付けが終わって帰れると思ったら、今度は飲み会があります。
神社界では「直会(なおらい)」と呼んでおり、氏子さんや関係者らとの重要なコミュニケーションの場となっています。神社界の飲み会は、今の感覚と比べると非常に激しいかもしれません。
朝方まで飲んで、そのままお祭り二日目を迎えることもザラにあるようです。
全国の神職さんが同じようなタイプとは言い切れないですが、実はタバコを吸う神主さんも多いので、直会は昭和のような飲み会が見られるのではないかと思います。
因みに筆者のところではコロナ禍を機に氏子さんたちとの直会は中止してます。すっごい楽です。
神職の仕事 依頼に基づき行われる祭り
七五三や厄除け、地鎮祭に加えて神前式(神社での結婚式)などのことを指します。
これらは祝詞の内容が異なるだけで、ご祈祷の内容はだいたい一緒です。七五三や厄払いなどのご祈祷は20分ほどで終わり、地鎮祭でも30分程度で終えます。
頻繁に行うので、すぐに慣れて大変なご祈祷ではないです。
ですが、前段階で準備が重要になのです。
例えば七五三のシーズンである11月だと一日に何十組のご家族がくるので、子供たちに渡す千歳飴の準備に加えて、独自に用意した受容品(記念品)を超大量に用意しなければいけません。

これは、厄払い・地鎮祭でも同様のことが言えます。
筆者が奉職している神社での厄払いシーズンだと一日に200組以上来ることもあるので、この時は七五三よりも受容品を準備する必要があります。
「やっと終わったー」と思っても、すぐに次のシーズンの準備に取り掛からないといけません。そんなことが続いていくと、もう正月がやってきます。
それぞれのご祈祷はバラバラでも、大まかな流れは一緒です。
神職の資格を習得する際に基本的な作法は学びますが、あくまで基本です。
ところが、現場に立つと通用しない場面もあります。神社によって独自の作法や順番が存在します。
仏教の宗派によっては「今何をやっているか分からない」となるらしいですが、神道はそういうことは起きません。マニアックなところの差異って感じです。
具体的に言えば、厄払いの祝詞でも神主さんによって選ぶワードが違ったり、それぞれの神社で口上のリズムが異なってきます。
もし神社へ行った際に生で聞く機会があれば、お祓いの作法と祝詞を地元の神社と比べてみるのも面白いと思います。
神職の仕事 社務所
お守りやおみくじ、御朱印の授与、祈祷の受付けがメインになります。
彼らを見て「単純作業で楽そうだな」と、思ったことありませんか?神職になる前まで、いつも思っていました。
会社員のように怒涛の時間が過ぎることもありますが、常に人に見られるため気が抜けた様子を見せれません。なので姿勢よく背筋を伸ばす必要があります。
ただ正直に書くと人が居なければダラダラして、人の気配したら瞬時に仕事している雰囲気をだしているだけです。
他には新たな祝詞を作成したり、普通の会社員のように資料作成をしています。
また参拝客からの質問に答えたり氏子さんとのコミュニケーションを取るのも大事な仕事です。
電話やメールでも問い合わせが来るため、答えられるように勉強する姿勢は持ち続けないとダメです。神職でも分からないことは沢山あります。
日本の歴史とも深く関わっているので、この勉強もしなければなりません
参拝者の中には神職よりも詳しい知識をお持ちの方も少なくありません。そんな人物が登場すると、なに聞かれるのか心配になって、ビクビクしてしまいます。
造詣の深い方からの質問は対応できますが、スピリチュアル系の参拝者の相談は答えられません。
神職は見えたり神様からのお告げも受け取る事は出来ません。
知識も無いんです。全国の神職の中に1人くらいは見つかるかもしれませんが、たいていは普通の人間です。
無下に出来ないので、不安を解消させるために協力は全力でしています。
意外と知られていない裏側の仕事内容
ここからは参拝客の目に触れない部分、もっと裏側の仕事についてご紹介します。神社の規模が小さいほど仕事は多岐にわたり、規模が大きいほど細分化されています。
また一般の企業の新人と同様に、若い者ほど泥臭い仕事を頑張らないといけません。
神職の仕事 清掃
神職の基本の仕事といえば、
清清掃です。
これは年齢が上がっても立場が上でも変わらない基本中の基本です。「礼で始まり礼で終わる」と似ています。
常に清掃しますし、大きい祭祀の前にも御社殿や境内の清掃は必ず行います。
「掃き清める」という言葉があるように、神社は清潔に保たれなければいけません。
落ち葉が塵積って雑草がボウボウの「何か怖い」と感じる神社よりも、「お参りに行くとホッとする」と思ってくれるように神主さん達の影の努力による部分も大きいと考えます。
普通はほうきで境内を掃きますが、時々ブロワーで一気にしたりしてます。
美しい桜の花や紅葉シーズンは落ち葉がね。マジでやばいです。雪が降る地域だと雪かきもあります。参拝者が安全に歩けるように、いつもより早めに来て雪かきをしている神主さん達もいます。
本当に大変です。
神職の仕事 事務系の仕事

神社でも文書作成やHP更新、メール問い合わせ対応などでパソコンは必須アイテムです。時にはスマホで仕事を行っていることもあるので、「あの人サボってる」と思わないで欲しいです。
社報の作成やご祈祷後に渡す受容品をまとめたり、おみくじの在庫確認&発注といった作業を社務所の受付けと平行しつつ行っています。
今の若い世代なら何も問題は無いと思いますが、神主を目指す人なら最低限のPCスキルとして、ワード・エクセル等のスキルは身につけていた方が良いです。
またHPは自前で更新しているところも多いため、簡単なweb知識もあれば戦力になりますし、SNSでの情報発信力が優れていると結構重宝されると思いますので、面接のアピールポイントになります。
未だに前時代的な考えや仕事が残っている業界ですが、PCスキルは出来るのが前提で仕事が進みます。
何故かパソコンやインターネットを否定的に考える宮司さんもいらっしゃいますが・・・
神職の仕事 勉強
これは神社界だけでなく、どこの会社に行っても変わりませんよね?
筆者は代々神社の家系の人間ではありません。
一般家庭の人間が神職になったので「ナニソレ知らない」と思うことばかりです。
神道と日本の歴史、奉職している神社の歴史、お祓いの作法、話術や経理関係(簿記3級程度)も必要です。また神社=御朱印と考える人も多いと思います。
書道がうまいだけでも非常に重宝されます。
筆者は習い事で習っていたことが今役に立っています。
他には暗算が得意だと良いです。神社ではキャッシュレスは全く進んでいません。
現金のやり取りが中心で業務が行われます。普段なら暗算が不得意でも問題はありません。
しかし、年末年始になると話が変わります。
あらゆるお守りの注文が入り、人によっては一万円以上買い求める参拝者がいます。瞬時に合計金額お伝えなければなりません。
とりあえず電卓は用意されていますが、それを使えないくらい年末年始は忙しくなります。

神職の仕事 宿直
神社に泊まって深夜に仕事をします。
中、大規模の神社ならほぼやっていると思います。筆者が奉職している神社では、この宿直を中止しているので具体的な内容を知りません。
先輩神職に聞くと、一晩神社に泊まって数時間仮眠とった翌日、定時まで通常の業務を行っていたそうです。ただでさえ休みが少ないのに、プラスで宿直は心が折れそうですね。
別の神社の神主さんの体験によると、宿直は月5回。夜21時と深夜2時に境内の見回り。朝5時に起床して鍵を開ける。7時に太鼓を叩く。その後は定時まで仕事だそうです。
読むだけでも大変なスケジュールですね。
宿直は神社によって仕事内容が異なるため一概に言えませんが、だいたいこんな感じです。コレが当たり前って、ブラック企業と感じちゃいますね。
神社を辞めてしまう原因にもなっています。
神社の仕事 お祭り
神社では毎日お祭りをやっているって知ってましたか?
それが「御日供祭(おにっくさい)」。筆者が奉職している神社では「ニック」とよんでいます。
これは神様にご飯をお供えする祭りです。
朝だけの神社と朝夕する神社、朝昼晩と3回行う神社もあります。
お供えするものも神社によって多少異なりますが、米・塩・酒・水の四種類は必須です。氏子さんから奉納された果物とかを一緒にお供えすることもあります。
それと毎月やるお祭りとして月次祭(つきなみさい)があります。
国家や氏子さんの安泰を祈るお祭りで月初めの1日に行います。1日だけの神社と15日に行う神社があります。
早めの時間帯に行われるため、神社のご近所さん以外は知らない人も多いと思います。
地域の人であればどなたでも参加できます。そして神職が3分程度の講話をしています。コレも大変なんです。ネタ探して話す内容を考えるのが。
神社の仕事 まとめ
神主の仕事内容について紹介しましたが、皆さんはどう感じました?
ハッキリ言うと、神社業界はブラックです。本当に。
これが現実なんです。
お祭りやお祓いなど一見優雅に見えても、ソレはあくまで一部分です。普段は雑用のような業務が主な仕事になります。
また”親ガチャ”のように神社界にも神社ガチャ”や”宮司ガチャ”的なモノがハッキリあります。
神社系ブログで記事を書いている人が元神主が多い理由は、ガチャに外れてしまった方々です。
テレビで常に紹介されているような有名な神社でも「あそこは超絶ブラックだから就職辞めとけ」ってものが普通にあります。
逆に地方のあまり有名ではない神社が隠れホワイトだったり、しっかりと地域特有の閉鎖的考えの神社も存在しています。
筆者は、元々ブラック企業に勤めていた会社員だったので、今の奉職している神社でブラック企業だなと感じることはないです。
また宮司さんも業界的には若い年齢なので、昔ながらの体制をだんだんと払拭しているので、働きやすい神社だと思っています。
最後まで読んでくれてありがとう
良い一日を。
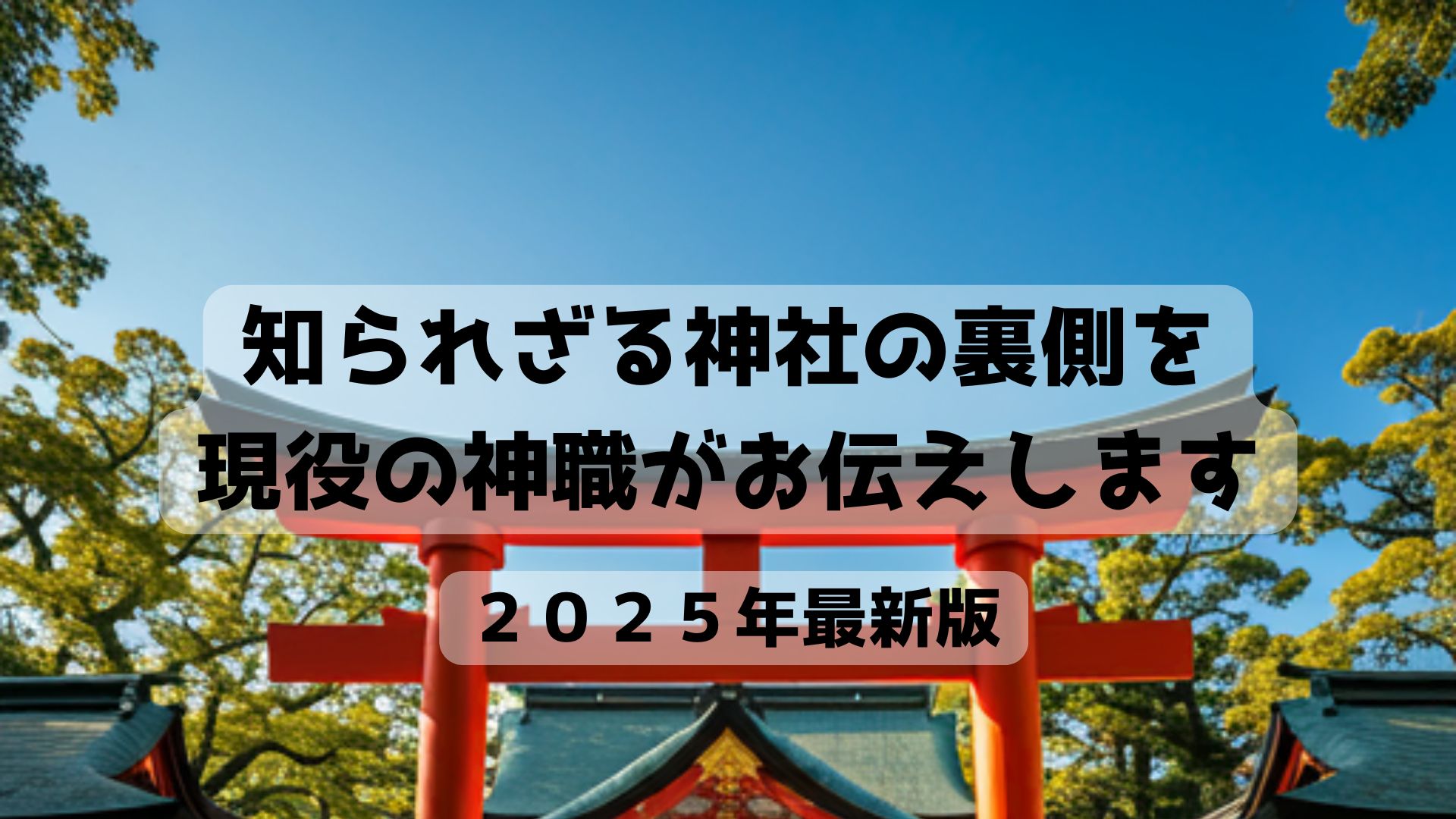

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46b17117.d591218f.46b17118.2b958830/?me_id=1349310&item_id=10000440&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Facross-zakka%2Fcabinet%2Fbaby%2F100d-kzr-top.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46b17c47.b8205794.46b17c48.2864cb5e/?me_id=1322884&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzaiho%2Fcabinet%2Fitem%2Ftokusan%2F581-c1_m_03.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)