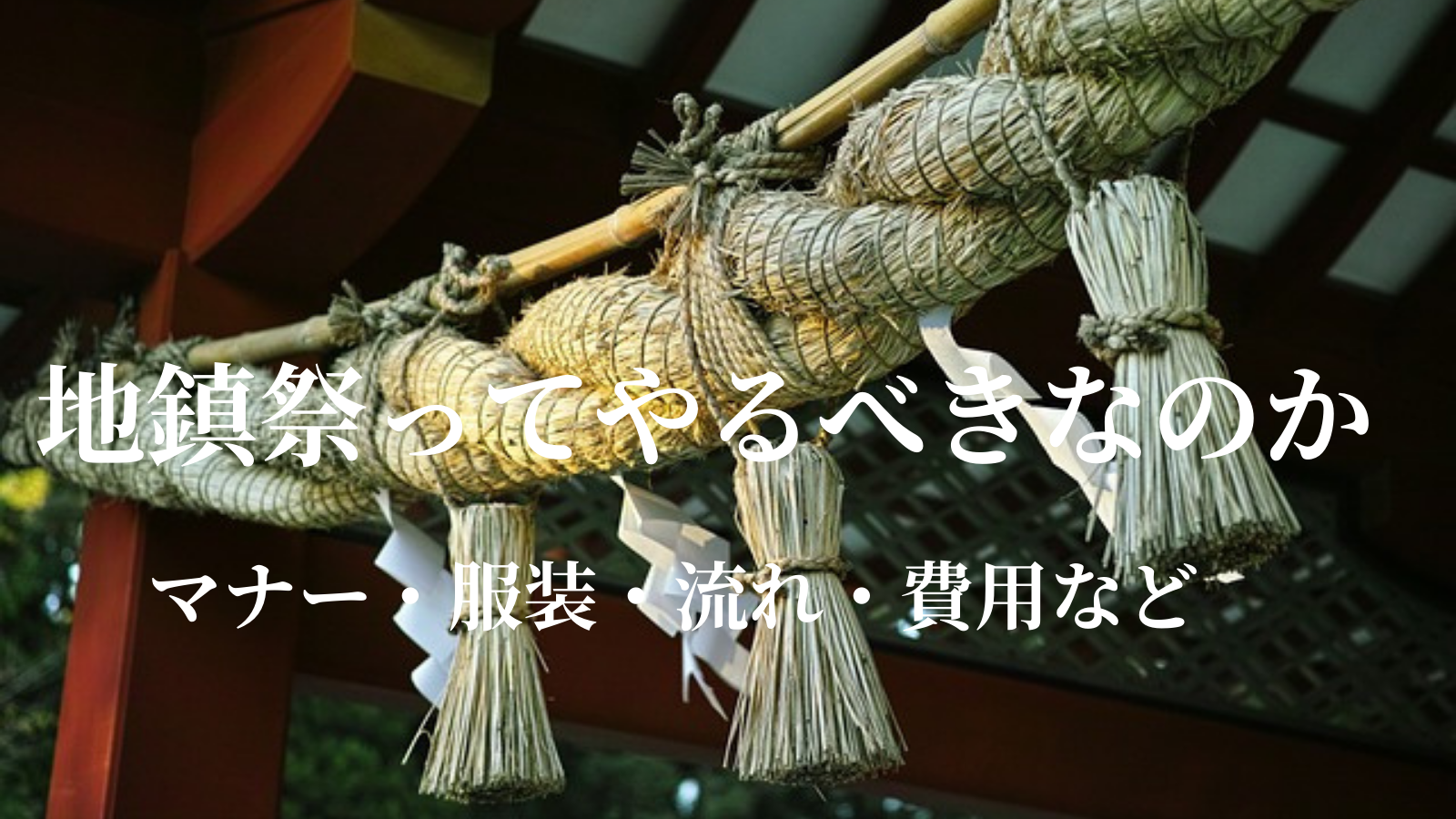遂に夢見ていた我が家を建てることになって、嬉しい気持ちと少し不安な気持ちが混ざっていると思います。
さて地鎮祭はどうされますか?そもそも「地鎮祭」ってご存知ですか?
今回は現役の神主である私が、地鎮祭について詳しく説明します。
そもそも地鎮祭や上棟祭などの建築儀礼は、必ず行なうべきことなのか。
結論
やっぱり行なうべき
我が家を建てることは人生において一大事です。
建築儀礼である地鎮祭には建主と建主のご家族だけではなく、建築会社や大工さん、あらゆる職人さんたちも参加して行われるのが一般的です。
家を建てる工程とその後の暮らしの平穏無事を願う重要な儀礼です。
地鎮祭 地鎮祭ってなに?
氏神様や土地に繋がりがある神様をお招きして、お供えものを捧げて祝詞を奏上します。
建主の土地を祓い清め工事の安全と無事に完成、家の繁栄をを見守ってもらうための建設儀礼です。
地鎮祭の歴史は結構古く、1300年以上前に完成したと言われている日本最古の歴史書である『日本書紀』にも、地鎮祭のことは書かれています。
つまり、それよりも古い時代から今日まで脈々と行われてきた伝統儀式だと言えます。
地鎮祭 地鎮祭の日程の決め方
家族が参列できる日で大丈夫です。
都合の良い日を神社や施工会社に連絡して日程を決めて下さい。
ただ、土用の日、不成就日、三りんぼうの日は避けた方がいいかもしれません。
土用の日
この日は、土地の神様が土をイジられることを最も嫌う日と定められています。無視して行なうと神様が機嫌を損ね、祟りを引き起こしてしまう可能性があります。
不成就日
地鎮祭に限らず、婚礼関係や引っ越し願い事など、あらゆることが始めると良くないとされています。
三りんぼう
地鎮祭よりも上棟祭を行なってはいけないと言われている日ですが、近年では建築関連のことは全て良くないとされています。文字通り「この日に建築関連のことをやってしまうと三軒隣まで滅ぼす」と言われています。
代表的な日はこの3つです。施工会社は他にも独自に縁起が悪いと考えている日もあります。
地鎮祭を行なう日を調整してくれると思います。
地鎮祭 参列する時の服装
特に決まりは無いです。
フォーマルな服装が一般的と言われています。ただ地域的なこともありますし、正直なことを言うと筆者が行く地域は完全な私服でも問題はありません。
しかし、短パン・サンダルなどのラフ過ぎる服装は避けるべきです。
企業や市町村が行なう地鎮祭に参加する機会があるなら、必ずスーツで参列すべきです。
地鎮祭 参列に用意するもの
神様に崇敬の気持ちを表し捧げる「初穂料」と祭祀に必要な神饌(お供え物)を用意します。
初穂料の金額は地域や神社によって異なります。
基本的に施工会社から金額を伝えられると思います。神社に問い合わせをすると「◯万円ですね」と答えてくれます。
神社によっては単に「お気持ちで。」と具体的な金額を伝えてくれないこともあります。
もし具体的な金額が分からなかった場合は、ネットで調べた地域の相場+1万円を加えた金額で大丈夫かと思います。
神饌の種類
米・酒・餅・魚(鯛)・卵・乾物(昆布やスルメなど)・野菜・果物・菓子が基本となっています。
神饌の準備は施工会社が用意する場合と神社に依頼して用意してもらう場合もあります。もちろん自分たちで用意しても問題ありません。
フルセットを用意するのは難しいので、米・酒・酒・乾物・野菜・果物だけでも大丈夫だと思います。
乾物と野菜、果物などは3種類ずつだとちょうど良いと思います。
企業の地鎮祭ではないので、餅や卵、菓子は別に用意しなくてよいと、筆者が奉職する地域は考えられています。
できる範囲で用意して貰えばいいですが、祭壇の上に神饌がポツポツと少ない状態だと、寂しい雰囲気になるので、たっぷりと用意してもらいたいです。
その他の祭壇を組むための机や神饌を置くための皿や三方などは、施工会社が用意してくれる場合と神社が用意してくれる場合があります。
地鎮祭 祭祀の大まかな流れ
地鎮祭のザックリとした流れを紹介します。
修祓 神主さんが祭壇と参列者を祓い清める
降神の儀 神籬(ひもろぎ)に神様をお迎えする
献饌 すでに準備されているお供えものを捧げる。お酒の蓋を取るだけのことが多い
祝詞奏上 神主さんが神様に工事の開始の報告をして安全祈願の祝詞を奏上する
散供 神主さんが敷地の四隅と中央(盛り土)に切麻
穿切の儀(うがちぞめの儀)神様に工事を告げる
0設計者が鎌で「えい、えい、えい」と言いながら草を掴んで刈る動作で抜き取る
1盛砂を館主クワで「えい、えい、えい」と言いながら3回崩す
2盛砂を施工会社の代表者がスキで「えい、えい、えい」と言いながら3回崩す
※筆者が奉職している神社の地域は、個人宅で穿切の儀の0を行なうケースは少ないです。
鎮め物埋納 神主さんが清めした鎮め物(木札)を土に埋める。
筆者が奉職している神社の地域では、穿切の儀と鎮め物埋納をすることは少ないです。
玉串奉奠 建主から玉串を祭壇にお供えして二礼二拍手一礼の作法でお参りする。
撤饌(てっせん)お供えした神饌を下げる。お神酒の蓋を閉める。
昇神の儀 神主さんが神様を送りかえす。
直会(なおらい)参列者全員で神様にお供えしたお神酒や神饌をいただく。
以上の手順が一般的に行われる祭祀の内容です。地域や神社によって作法順番に違いがあります。
参列者にしてもらうのは、穿切の儀と玉串奉奠、そして地鎮祭が執り行われた後に、米・酒・塩・水を撒いてもらう事もあります。
地鎮祭 なぜ地鎮祭をすべきなのか
「なんの意味があるの?」と思う人もいるかもしれません。
でも自分が住む土地の神様に挨拶せず、家を建ててくれる職人達の安全と無事も願わないのは、感じが悪くない?と思います。その土地に住み続けるのに何もしないのは逆に怖くないですか?
考えて欲しいのですが、恋人との結婚を決めた際に義両親へのあいさつは最低限必要だと考えますよね。感覚はそれと同じです。
しかし、“地鎮祭”の文化は、年々薄れて来ています。
最近の工務店の社員の中には「そんなの必要ない」と断言してしまう人もいます。また勝手に社員がオリジナルの地鎮祭をして勝手に済ましてしまう事例もあります。
購入した土地は元々なんだったかご存知ですか?そこの地域の歴史もしっかりと把握していますか?「住み始めて最近良くないことが続いているな。」となってしまったら、なんか嫌じゃないですか。
本当かどうか分かりませんが、年配の神職に聞くと土地に関する奇妙な話を聞くことがあります。本当なのか判断が出来ない話を聞いてしまった以上、地鎮祭は必ず行おうと個人的に考えています。
地鎮祭 セルフ地鎮祭のやり方
SNSで時々「セルフ地鎮祭のやり方」と言った情報を発信している人を見かけますが、アレは地鎮祭では無いです。単に米と塩・酒を自分の土地に撒いて汚しているだけです。
地鎮祭のデメリットとして挙げられるのは、料金だど思います。
たった数十分の儀式のために数万円が飛ぶことに抵抗を感じるかも知れません。
地鎮祭は祭祀です。
神様と一般の方々との間を取り持つ専門家として神職がいます。また祭祀にも細かい決まり事があります。何より建主の家の繁栄と職人達の工事の安全を全力で祈願しています。
車の整備も資格を持った整備士さんに頼みたいですよね。手術を受けるなら医療免許を持った医師に依頼すますよね。
それぞれの分野で専門のプロがいます。
セルフ地鎮祭をして、祟りが怖いから大昔に一応祀っていた禍々しいモノを、もし引き寄せてしまったら超最悪じゃないですか。
地鎮祭は我が家を建てるための重要なスタートだと思います。あらゆる人達が関わり、あなたの素敵な家を建ててくれます。正式なスタート(地鎮祭)をすべきだと思います。

地鎮祭 まとめ
地鎮祭は家族のためであり、関わる人達のための儀式です。
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
良い1日を。
良い1日を